PR
マイホームを作ろう!と思ったのはいいものの、
- いくらくらいお金は必要?
- 頭金ゼロでも大丈夫?
- そもそも、どうやって作ればいいの?
など様々な疑問が出てきますよね。
一般的に、年収を5倍した数字が余裕をもって返済できる物件価格と言われています。
また、頭金ゼロでも建てられますが、ある理由からおすすめできません。
記事では、マイホームの作り方から気になるお金のこと、そして参考にすべき情報源などを紹介します。
この記事を読めば、マイホームを建てるのに必要なお金や制度、作り方などがばっちり分かります。
また本文に入る前に、家づくりにおいて最も重要なことを伝えさせてください。
マイホームを建てたい!と考えたら、何よりも先に始めなければならないことがあります。
それは、「出来るだけ多くの住んでいる地域に対応している住宅メーカーの資料集めすること」です。
ここだけの話、家づくりで後悔している人のほとんどは、この「住宅メーカーの比較」を怠っていたというケースが非常に多いのです。
例えば、5,6社見ただけで住宅展示場で一目惚れした家に決めてしまったり、営業の人の話に流されてしまったり・・・。
ほとんどの人にとって家は一生に一度の大きな買い物。
後から、改築や建て直しをすることになり、何千万円もの損をしてしまう方も実際に存在します。
そんな失敗をしないためにも、事前に多くの住宅メーカーのカタログを集め1度は比較してみることが何よりもまず最初にやるべきことなのです。
「でも数多くある住宅メーカーからカタログを取り寄せるなんて、時間もかかるし面倒くさい」
ほとんどの人がそう思うでしょう。
そこでぜひ活用してほしいのが、SUUMOのカタログ一括請求サービスとNTTデータグループが運営する家づくりのとびら。
マイホームの建設予定地を入力するだけで、そのエリア対応の住宅メーカーのカタログをスマホから簡単に取り寄せることが出来ます。
SUUMOでは工務店を中心に、家づくりのとびらはハウスメーカー中心に無料で資料を取り寄せられます。
「予算的にハウスメーカーは厳しい。。。」
「絶対に知名度のある会社がいい!」
このように先入観を持つのではなく、まずは必ず1度出来るだけ多くの住宅メーカーに目を通して下さい。
最初は比較対象じゃなかった会社や、名前も知らなかった会社が実は自分たちにとってはベストな住宅メーカーだったという方は非常に多いです。
後から取り返しのつかない後悔をしないよう、面倒くさがらず資料を取り寄せてしまうことをおすすめします。
それでは解説を進めていきます。参考にして下さい!
もくじ
- 持ちたいマイホームのイメージを考える
- 買えるマイホームの価格をシュミレーション
- マイホームを買うのに頭金は必要?無しでも大丈夫?
- 夢のマイホーム!マンションにするか、一戸建てにするのか
- マイホームを注文住宅で建てるメリット・デメリット
- 分譲住宅をマイホームにするメリット・デメリット
- マンションをマイホームにするメリット・デメリット
- マイホーム購入をする際の情報収集の仕方を不動産のプロが解説
- マイホーム購入時における住宅ローンの組み方と審査方法
- マイホーム購入から引き渡しまでの期間と流れ
- マイホームに入居するまでに必要な手続きや書類と流れ
- マイホームを購入した後に必要なお金
- マイホーム購入ブログ3選
- マイホームを買うのに参考になる本や雑誌
- マイホームの失敗事例~後悔しない為に知っておきたい3つのこと
- まとめ
持ちたいマイホームのイメージを考える

マイホームを作るとき、まず考えるべきなのが完成形のイメージです。
100%理想通りにするのは難しくとも、理想像は常にゴールとなります。
とはいっても、持ちたいマイホームのイメージが作れないという方もいるはずです。
建てたいマイホームを考えるときは、まずは新しい暮らしをイメージしてみてください。
広々としたリビングで家族の時間を過ごしたい、家事が楽に行える家がいい。
どこにいても子どもたちを見守りたい、ガーデニングや家庭菜園などを楽しみたいなど、様々な想いがあるはずです。

新しい暮らしは、マイホームのテーマとなります。
家族全員に希望を考えてもらって、それをノートに書き写すといいですね。
ここで注意点が1つあります。
この段階で、予算の心配をする必要はありません。
大切なのはマイホームに求めることを明らかにして、それを建築会社に伝えることです。
予算内に収めようとしては、思い描いた住宅は作れません。

しかしながら、予算の問題で必ずしも全ての要望が叶うというわけでもありません。
そこでおすすめしたいのが、要望に順位付けすることです。
- 絶対に叶えたい要望
- できれば叶えたい要望
- 叶ったらラッキーと思える要望
この3つに分類してください。
そして、絶対に叶えたい要望から実現していくと、満足度の高いマイホームになるはずです。
マイホームの床面積は把握しておこう
マイホーム像を作るときは、床面積を把握しておきたいところです。
参考資料:床面積とは SUMMO
その理由は、全ての要望を実現するためには、敷地以上の面積が必要だったという失敗がよくあるから。
極端な話、要望を叶えるためには大豪邸にする必要があったということもあります。
そのため、土地面積を把握して、どのくらいの規模の家が建つのか把握しておきましょう。

買えるマイホームの価格をシュミレーション

マイホームは人生で最も大きな買い物の1つと言われています。
そのため、マイホームを購入すると決めたら、しっかりとした予算計画を立てなければいけません。
では、マイホームの適性額とはあるのでしょうか?
住宅金融支援機構が行った「フラット35利用者調査(2016)」によると、住宅購入にかかった平均金額は3,494.7万円と判明しています。
参考資料:フラット35利用者調査(2016)住宅金融支援機構
でも、年収によって支払える額が異なるのも事実です。
年収300万円の方と800万円の方では、同じ3,000万円の物件を買うとしても、負担が大きく異なりますよね。
一般的に、年収の5倍の価格がゆとりをもって購入できる額だと言われています。

つまり、年収500万円の方なら2,500万円、800万円の方なら4,000万円がマイホームとして適性額なのです。
住宅金融支援機構の調査では、年収の平均6.5倍が住宅購入資金だと判明していますが、多少無理をしたとしても6倍で収めるのがおすすめ。
年収の6倍以上の物件を購入するとなると、住宅ローンの借入額が大きくなってしまい、返済が負担になってしまう可能性が高くあります。
マイホームを買うのに頭金は必要?無しでも大丈夫?

頭金とは、購入するときに支払える現金のことです。
一般的に、マイホームを購入するとなると、頭金+ローンの組み合わせが支払い方法になると思われます。
さて、結論から言うとマイホーム購入時に頭金はあった方がいいです。

しかし、合ったほうがいいだけで、頭金がなくとも住宅購入はできます。
実際に、最近は頭金がなくとも融資してくれる住宅ローンが増えています。
それなのに、頭金を用意しておいた方がいい理由は何でしょうか?
1つ目の理由は、頭金があるほうが住宅ローンの借り入れがしやすくなるからです。
頭金があるほど、借入額が少なくなりますよね。
だから、住宅ローンの審査に通りやすくなるのです。
2つ目の理由が、住宅ローンの借入額が少なくなるから。
はっきり言えば、住宅ローンを借りないで済むのなら、借りないほうがいいです。

住宅ローンにも利息があるため、借入額よりも大きな額を返済しなければいけません。
ただ、現実にはそうもいきませんよね。
だから、頭金を用意して借入額を少なくするのです。
そうすることで利息と返済額を抑えられます。
以上2つの理由で、マイホーム購入の際は頭金を用意しておくべきなのです。

では、どのくらいの頭金を用意しておくべきでしょうか?
よく言われるのが、住宅価格の20%を頭金として準備し、残り80%はローンに充てるということ。
そのため、最低でも住宅価格の20%は現金で支払えるようにしておきましょう。

3,000万円の物件なら600万円を頭金として用意しておくということですね。
頭金がなくとも住宅購入はできますが、十分な額を貯蓄できていないなら一旦ストップしたほうがいいかもしれません。
頭金がほとんどないということは、これまで貯蓄ができていないということです。
今までの家賃分を返済に充てるという考え方もできますが、それでは教育費や老後資金の貯蓄が難しくなってしまいます。
まずは家計を見直し、物件価格の20%を貯蓄することを当面の目標にしてみてください。
マイホーム購入時における頭金の準備方法
頭金の準備方法は貯蓄だけと思われがちですが、もう1つ活用したい方法があります。
それが親からの援助を受けることです。

なんと住宅購入目的で親から援助を受ける場合は、贈与税がかからない可能性が高くあります。
ここからは、2つの頭金準備方法について解説します。
マイホーム購入には貯蓄がある程度必要
地道な方法ではありますが、貯蓄が一番の近道です。
現在は金利が非常に低いですが、やはり安心安全の積立預金などが一番でしょう。

また、投信積み立てや個人国債はリスクが低いうえに、銀行預金よりもハイリターンの可能性があります。
逆に株などはハイリスク・ハイリターンなので、頭金の用意方法としてはおすすめできません。
また、会社員で財形住宅貯蓄を利用できるなら、活用するといいかもしれません。
時間こそかかりますが、貯蓄が確実に頭金を貯める方法です。
「でも、頭金が貯まるまで何年も待てない!」という方もいるでしょう。
そのような方は、これから紹介する親からの援助を検討してみてください。
両親からの援助がある場合はマイホーム購入も有利
両親からの援助は主に2つの方法に分けられます。
1つ目は、親からお金を借りる方法です。
親から頭金を借りることで、無理なく返済できます。
借金をする場合は、借用書などを作り、お互いに署名捺印をしておきましょう。

これを怠ると贈与税の対象になる可能性が出てきます。
ある意味で、借用書などは贈与税を免れる証拠となるのです。
また、両親に手渡しでお金を返すのもNG。
両親の銀行などに振り込んで、返済も記録として確実に残しましょう。
注意点としては、親からの借金でも利息ゼロは認められないということ。

自由に利息設定はできますが、利息ゼロだと「利息分は贈与した」と思われる可能性があるのです。
2つ目の方法が、親から贈与として資金を受け取ること。
贈与だと多額の贈与税がかかると思われていますが、住宅購入資金なら話は別です。
親から子へ住宅資金の贈与をするときは、2,500万円まで贈与税免除の対象となります。

2,500万円を超えた部分は、20%の課税となってしまいますが、それほど多額の援助を受けることはほぼないでしょう。
もし両親が死亡すれば、それまでの贈与金額と親の財産を加え、その合計金額を新たに相続します。
しかし「法定相続人の人数×1,000万円+5,000万円」が基礎控除額となっているため、合計金額がこれを越えなければ相続税はかかりません。
つまり、この制度をうまく活用すれば、相続税が一切課税されずに頭金を用意できるのです。
優れた制度があるとはいえ、まとまった金額が動くのは事実。
まずは両親や家族と話し合って、頭金をどのように準備するのか考えましょう。
マイホームを買うのはいつ?年収や年齢とタイミング
この記事を読んでいる方の中には「いつマイホームを購入するのがいいのだろうか」と疑問に思っている方もいるでしょう。
消費税率の引き上げや東京オリンピック開催などの気になるイベントがあれば、年収や年齢も気になりますよね。
ここからは、マイホームを買う年齢・年収とタイミングについて見ていきましょう。
マイホームを買う年収と年齢はいつが良いのか
国土交通省が実施した「住宅経済関連データ(2016年)」によると、戸建て購入者の平均年齢は38.9歳で世帯年収は646万円、マンション購入者は43.3歳で世帯年収は835万円と判明しています。
このデータを見ると、仕事もかなり落ち着いた世代がマイホームを購入しているように思われます。

職種にもよるでしょうが、30歳代後半になると転勤や転職などの可能性は低くなり、社内でも役職についていて年収が安定している方が多いでしょう。
また、年齢が高くなると長期間のローンが組めなくなるというデメリットがあります。
若すぎず、年齢が高すぎない30歳代後半から40歳代前半が、マイホームを買ういい年齢なのかもしれません。
マイホームを買うタイミングはオリンピック前・後?増税前・増税後?
実は不動産業界は立て続けに大きなイベントを迎えます。
2019年10月に実施される予定の消費税率引き上げ。
その翌年には、東京オリンピックが待っているのです。
1つずつ疑問を解消していきましょう。
まずは消費税率の引き上げについて。
1つ覚えておきたいのが、2019年10月1日以降に物件の引き渡しをされても、消費税8%で購入できる場合もあるということ。

住宅代金の支払い並びに課税は、物件引き渡しを基準に行われます。
だから、2019年10月1日までに完成させようと、焦っている方もいるでしょう。
しかし、住宅購入資金の課税は特別スケジュールが組まれています。
増税の半年前(2019年4月1日)までに契約していれば、引き渡しが増税後になったとしても消費税8%のままなのです。
この増税スケジュールは覚えておきましょう。
また、消費税増税経過措置を利用すれば増税しても損はしません。
代表的な経過措置が以下の2つ。
住宅ローン控除をマイホーム購入に活用する
10年以上の住宅ローンを使用して、住宅購入をした際、所得税の控除を受けられる制度です。
10%の消費税が課される人でも、2021年12月31日まで入居すれば、10年間の控除を受けられます。
すまい給付金をマイホーム購入に活用する
消費税率引き上げによる住宅購入者の負担を軽減するために作られた制度です。

参考資料:すまい給付金
住宅ローン控除は所得の多い人ほど得する制度ですが、すまい給付金は高所得層と低所得層の負担の差を縮めます。
すまい給付金は、物件を消費税8%のときに購入したか、消費税10%のときに購入したかで給付金額が異なります。
消費税率8%のときは、約510万円以下の収入の方を対象に最大30万円の給付金が支払われます。
対して消費税率10%のときは、約775万円以下の収入の方を対象に最大50万円の給付金が支払われるのです。
ただし、すまい給付金は消費税が適用される物件のみの対象となります。
つまり、消費税のかからない中古物件だと、給付金の対象とならないのです。
自分の年収などを考えて、消費税増税前と後ではどちらが特になるのかをチェックしてみるといいでしょう。

どちらにせよ、消費税増加前に購入しなければ大損するということはないでしょう。
「増税前だから今がチャンス!」と言う業者に惑わされないようにしましょう。
気になるのが東京オリンピックです。
オリンピック・パラリンピックに向けて、建設ラッシュが進んでいますが、開催後は景気が減速する可能性があると言われています。
2020年以降だと割安で住宅購入できるかもしれませんが、これはあくまでも可能性の話。
実際に住宅価格が下落するとは限りません。
そのため、東京オリンピックまで待つのは得策とは言えません。
 スポンサードリンク
スポンサードリンク
オリンピックよりも気になるのが金利の行方です。
現在の金利は史上最低水準で、住宅ローンを組むうえでは非常に有利。
ローンは引き渡し時の金利が適用されます。
そのため、引き渡し時の金利が契約時よりも高くなっていれば、大きな損をすることがあります。

住宅ローンは借入額が大きいため、たった2%の違いが1,000万円以上の差を生み出すことだってあるのです。
納得いくタイミングでマイホーム購入できるように、常に勉強を行っておく必要があります。
夢のマイホーム!マンションにするか、一戸建てにするのか
 マイホームとして人気なのがマンションと一戸建て。
マイホームとして人気なのがマンションと一戸建て。
なかなか決めるのが難しいですが、何よりも先にどちらの物件タイプにするのか決めることが大切。
そうすることで、理想のマイホームに最短距離で近づけます。
一戸建てもマンションもメリット・デメリットがあり、それらは次の項から詳しく見ていきましょう。
ここではライフスタイルを中心に、物件タイプを考えていきたいと思います。

理想のマイホーム作りには、家族構成や年齢、ライフプランなどを考慮しないといけません。
例えば、お子様がいるもしくは将来的に子を持つ予定の方は、住み方に自由がきく一戸建てがいいかもしれません。
好きな位置に子ども部屋を作れれば、リビングから子どもを見守れる間取りも作れる、そして生活音を気にしなくていいのは一戸建てならでは。
立地条件の良さや防犯性を重視するのなら、マンションがいい選択肢になるでしょう。
やはり大切なのは、マイホームでどのような暮らしをしたいのか具体的にすることです。
マイホームに求めることを決め、優先順位をつけてください。

そして希望を1つでも多く叶えられる物件タイプが、あなたの理想の住宅となります。
マイホームを注文住宅で建てるメリット・デメリット
 こだわりのある家を作りたい方に、おすすめなのが注文住宅です。
こだわりのある家を作りたい方に、おすすめなのが注文住宅です。
戸建ての中でも、最も自由に住宅建築ができるため、理想のライフスタイルを実現できるでしょう。
そんな注文住宅ですがデメリットもあります。
ここからは、新築・中古注文住宅のメリットとデメリット見ていきましょう。
新築の注文住宅をマイホームにする場合
新築の注文住宅は、土地探しから家の設計、建築までゼロから行います。
そのため、最も時間がかかり費用がかかる住宅として知られているのです。
ただし、土地と住宅が資産となるため、総合的にみると資産価値はマンションよりも高くなるでしょう。
新築注文住宅の最大のメリットは、自由に住宅設計ができることにあります。
家族構成やライフスタイル、ライフプランに合わせた住宅設計ができるのです。

また、一戸建てなので足音や声などの生活音をあまり気にする必要がないため、子どもがいる家庭は注文住宅を選ぶことが多いです。
高価な費用はデメリットになりますが、建材や設備、間取りなどを工夫することで十分に抑えることも可能。
新築注文住宅のデメリットは、傾向的に利便性の悪い土地に住宅を建てることになること。
利便性のいい土地はあまり残っていなければ、価格もかなり高くなります。
そのため、駅から距離が遠い場所などに住宅を建てなければいけない可能性が高くあります。
さらに、10年ごとのメンテナンスが必要となるため、その修繕費用を積み立てなければいけません。

【メリット】
- 自由に設計できる
- 住宅だけではなく、土地も資産になる
- 生活音を気にする必要はない
- ペットを飼える
- 庭なども自由に設計できる
【デメリット】
- 約10年に1度のメンテナンスが必要
- 土地の利便性が悪い
- 高額な費用
中古の注文住宅をマイホームにする場合
注文住宅を検討している方は、中古物件も積極的に見ていきたいところです。
中古戸建ての魅力は、実際に物件を見て購入できるとこ。
新築の場合は、完成するまでどんな住宅になるのか分かりません。
完成してみると、描いていた住宅と異なったという可能性もあります。
しかし中古住宅の場合は、一度完成形を見てから購入できるため、納得のいく買い物となるでしょう。

また、リフォームをすることで好みの住宅を実現できます。
ただし、リフォーム内容によっては新築購入のほうがお得になることもあるので、事前に予算確認をするようにしてください。
デメリットは、デザインが古い可能性があること、そして内部構造が劣化している可能性があることです。
比較的予算に余裕のある方は新築注文住宅にして、予算に限りがある方は中古物件を視野に入れるといいですね。
【メリット】
- 実際に住宅を見てから購入できる
- リフォームをすれば好みの住宅になる
- 価格を抑えられる
【デメリット】
- デザインが古いかも
- 内部構造が劣化している可能性がある
分譲住宅をマイホームにするメリット・デメリット

よく耳にする分譲住宅ですが、どんな物件なのかご存知でしょうか?
分譲住宅とは、まとまった住宅を分割して販売された住宅のこと。
業者がインフラ整備をして大量に住宅を建て、それらを分割して一戸ずつ販売したりします。
ここからは分譲住宅のメリット・デメリットを解説します。
新築の分譲住宅をマイホームにする
分譲住宅の大きなメリットは、費用を大きく抑えられることにあります。
あらかじめ数多くの住宅を建てるため、資材などを大量発注してコストを抑えているのです。
また、デザインや間取りもシンプルなため、設計と建築費用もお手頃になっています。
このような理由で、分譲住宅は新築であっても比較的コストが安いのです。

また、すでに建てられた住宅なので、物件を見てから購入できるというメリットも。
分譲住宅ならではのメリットと言えば、利便性が良いことにあります。
一般的に、分譲住宅と一緒にスーパーや病院、学校なども建設されるのです。
デメリットは部屋の作りが非常にシンプルになるということ。
こだわりを重視する方は、注文住宅にしたほうがいいかもしれません。
マンションをマイホームにするメリット・デメリット

注文住宅と同じくらい人気なのがマンションです。
価格は高騰し続けていますが、それでも人気が衰え知らずなのはちゃんとした理由があるから。
さっそくマンションのメリット・デメリットを見ていきましょう。
新築のマンションをマイホームにする場合
住宅価格だけ見ると、注文住宅よりもマンションの方がお得です。
その理由は、多くの世帯で土地をシェアすることになるから。
ただし、土地が資産にならなければ、一般的に注文住宅のほうが広いということはお忘れなく。
マンションが人気の主な理由は、利便性と安全性が高いからでしょう。

多くのマンションは駅から近い位置にあれば、周辺にコンビニやスーパーがあることも多いです。
この立地の良さは、注文住宅ではなかなか実現できません。
安全性の面でいうと、多くのマンションがオートロックを導入しており、隣人がいることも防犯性へとつながります。
デメリットは、敷地面積に限りがあり、こだわりのある住宅を作れないことがあげられます。
また、修繕費の積み立てや管理費、駐車場代金などを毎月支払わなければいけないのもデメリットとなるでしょう。
【メリット】
- 駅近などの利便性が高い
- 安全性や防犯性が抜群
- 耐震性や耐火性に優れている
【デメリット】
- 敷地面積が狭い
- 生活音が気になるかも
- 管理費や修繕費などの支払いがある
- ペットが飼えない可能性が高い
中古のマンションをマイホームにする場合
中古マンションは、自分好みにリフォームしたい方におすすめ。
新築マンションをリフォームするとなると高額な費用がかかりますが、中古マンションならリフォーム費用を抑えられるのです。
ただし、マンションによってはリフォームにも制限があるため、事前に管理会社と相談しましょう。
また、利便性の高いマンションを見つけられる可能性が非常に高いのも魅力。
新築マンション数よりも、中古マンションの数のほうがずっと多いです。
選択肢は膨大なので、非常に利便性が高い中古マンションを見つけられる場合さえあるのです。

中古というとマイナスなイメージがありますが、中古マンションはきっといい選択肢となります。
マンションを探している方は、ぜひ中古マンションも候補に入れてください。
マイホーム購入をする際の情報収集の仕方を不動産のプロが解説
マイホーム作り成功には、情報収集が不可欠です。
主な情報収集方法は、
- ウェブサイト
- 書籍
- チラシ
- 物件見学
- フリーペーパー
この5つ。
ここからは、それぞれの情報収集方法のメリットを見ていきましょう。
ウェブサイトでマイホームの情報を集める
最も一般的な情報収集法が、ウェブサイトでしょう。
各建築会社の公式サイトや物件探しサイト、マイホーム建築ノウハウサイトなど情報量は圧倒的に多いです。

うまく活用すればいい情報収集手段となります。
ただし、気を付けておきたいのがネット情報の中には、信ぴょう性に欠けるものもあるといいうこと。
そのため、正確な情報かどうかを見極める必要があります。
ネットで有効活用したいサイトは以下の2つです。
建築会社公式サイトでマイホームの情報を集める
建築会社を選ぶときに、公式サイトは大きな情報源となります。
各会社の強みや得意住宅スタイル、そして大まかな値段が分かります。
また、多くの建築会社は住宅ギャラリーを載せているのです。

それらを参考にすることで、理想のマイホーム像が明らかになったり、住宅に関するアイデアを得られたりします。
スーモやアットホーム、ホームズでマイホームの情報を集める
物件探しサイトを賢く使えば、効率よく住宅探しを行えます。
一度検索してみれば分かりますが、ネット上には莫大な物件が掲載されているのです。
それらを1つずつ見ていては時間がかかりすぎるので、物件探しサイトでは絞り込み検索をするのがおすすめ。

住宅タイプから希望エリア、希望価格などを設定するといいですね。
また、物件探しサイトを利用することで、希望エリアの価格相場の目安が判明します。
上記のほかにも、気になる建築会社に関する特集記事や口コミ、さらには地盤情報までネットで調べることができます。
上手に活用できれば、間違いなく大きな武器になることでしょう。
書籍や雑誌でマイホームの情報を集める
書籍はネットよりも信頼性が高く、有益な情報が記載されています。
有料だからと手にしない方もいますが、何千万もするマイホームと比べると微々たる価格ではないでしょうか?
書籍を読むことで、いい建築会社を知れたり、賢いマイホームの作り方を学べたりします。
書籍を読むかどうかで、マイホーム成功率が大きく変わると言っても過言ではありません。
そのため、マイホーム作りに関する書籍や雑誌は積極的に読みましょう。
後ほど、おすすめの書籍を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
チラシ・フリーペーパーでもマイホームの情報は集められる
郵便ポストに入っている折込チラシもまたいい情報源です。
折込チラシでは間取りばかり注目されますが、それよりも物件概要という項目に注目してください。

物件概要には、建ぺい率や建物の容積率など建築基準法に関する情報が記載されているのです。
住宅作りは完全に自由に行えるというわけでもなく、建築基準法という法律に沿って建てられないといけません。
戸建てだと家族が増えたタイミングで増改築を行うのは一般的ですが、建築基準法違反で改築不可ということもあります。
そのため、事前にその土地の建築基準法条件に関してチェックすることが重要なのです。
また、駐車場利用料金や管理費なども参考になるポイント。
さらに、駅などに置かれているフリーペーパーにも良質な情報が詰まっています。

住みたいエリアのフリーペーパーをゲットしたら、折込チラシと同様に細かな情報までチェックしてください。
住宅展示場やモデルハウスでマイホームの情報を集める
各建築会社はモデルハウスなど物件見学を開催しています。
気になる建築会社があれば、ぜひ物件見学に出向いてください。
そこではネットや書籍、チラシなどでは確認できない情報が満載です。
そのため、建築会社へ依頼する前には、必ず物件見学を行ってください。
見るべきポイントは次の項で詳しく解説します。
住宅展示場やモデルハウスでマイホーム検討をする際のポイント
住宅展示場や物件見学では、実際に見ないと分からない情報が得られます。
例えば、間取り図では分からない天井高や雰囲気、動線、部屋の広さなどが分かるのです。

物件見学をすることで、あなたが住んでみたときの具体的なイメージが湧きます。
具体的なチェックポイントはすぐ後に見ていくとして、まずは物件見学への持ち物を紹介します。
マイホーム候補物件見学の際の持ち物と用途
- スマホもしくはカメラ :気になる部分は写真で保存
- メモと筆記用具:感じたことや気になったことは細かにメモして、後で見返そう
- メジャー:家具を置く場合のサイズ確認に便利
- 履物:様々なメーカーが一斉に住宅展示会を行っているので、スリッパなどが
あればスムーズ - チェックリスト:事前にチェックすることや、質問事項をメモしておこう
- カバン:住宅展示場では多くの資料を受け取るため、資料を入れるためのカバンは必須
そして、ここからは気になるチェックポイントを見ていきましょう。
マイホーム候補物件の大きさや雰囲気もチェックしよう
平面間取り図で見るだけでは、物件の実際の大きさや雰囲気は分かりません。
間取り図では広いのに実際に見ると狭い、その逆もあり得ます。
そのような物件に入ったときに受けた印象は細かにメモしておきましょう。

具体的には、天井高や窓の大きさ(どちらも部屋の空間に影響を与えます)、採光、廊下や階段の移動しやすさなどなど。
体験しないと分からないことを知れるのが住宅展示場のメリットです。
後で思い出せるように、写真やメモで細かに保存しておきましょう。
生活動線もマイホーム選びには超重要!
動線とは、建物内を人が自然に動いた時の経路を線で示したこと。
マイホーム作りで最も大切なのが、生活動線と言っても過言ではありません。
生活動線が悪ければ、長年住み続けると不満を感じる家になってしまいます。
洗濯機と洗濯場が離れた家をイメージしてみてください。
洗濯した洋服を遠く離れた洗い場まで何往復しながら運ぶのは、少し面倒じゃありませんか?
物件見学をするときは、実際にそこに住んだことをイメージしながら、部屋の中を見回りましょう。
家事はしやすい間取りかどうか、キッチンやリビングから洗面所などに行きやすいかどうかなど。
マイホームで暮らすことをイメージして設備をチェックしよう
住宅見学では部屋の設備も確認しておきましょう。
キッチンや水回りなどは実際に使うつもりで見てみてください。
またその際に、住宅設備は標準仕様になっているのかどうかも営業担当に聞くといいでしょう。

というのも、ほぼ全ての見学物件は最高級仕様となっています。
システムキッチンやお風呂などが決め手になったのに、同じ仕様にするには追加料金がかかるということもあるのです。
そして、標準設備のグレードアップはかなり高額。
設備は本当に必要かどうか、標準仕様かどうかを重点的に確認しましょう。
営業担当者はマイホーム選びの重要なパートナー
マイホームを建てるうえで、営業担当は重要です。
営業担当はその建築会社の窓口みたいなものであり、あなたの要望を建築会社に伝える橋のようなもの。
優秀な営業担当に出会えると、理想のマイホームを建てられる可能性がぐっと高まるのです。
では、あなたの営業担当はどのように決まるのでしょうか?
それは住宅展示場や物件見学で、あなたがアンケートを渡した相手です。

営業担当を変えることは可能ですが、なかなか言い出しにくいのが本音ですよね。
だからこそ、アンケートを渡す相手には十分に注意しましょう。
営業担当の質の良さを見極めるためには、実際に会話してみるのが一番。
人柄の良さは当然であり、そこに経験や知識がないと信頼できる営業マンとはいえません。
住宅展示場では営業に以下の質問をしてみてください。
- 入社何年目なのか
- その建築会社ならではの強み
- これまでの担当物件数
特に担当物件数は重要です。
住宅建築は計画通りに行かないことが多々あり、そういったトラブルに対応できるのは経験です。

また、不動産業界は入れ替わりが激しいので、結果を残していない人が営業担当になると、途中で担当が入れ替わってしまうということもあります。
営業はその建築会社の代表なので、素材や構造、アフターサービスなどの気になることがあればどんどん質問しましょう。
住宅見学が終われば、あとは家族で話し合いをするだけです。
各メンバーが感じたことを伝え合い、意見をノートにまとめましょう。
マイホーム購入時における住宅ローンの組み方と審査方法
 大多数の人が活用することになる住宅ローンですが、あなたは種類や組み方をご存知でしょうか?
大多数の人が活用することになる住宅ローンですが、あなたは種類や組み方をご存知でしょうか?
各住宅ローンのメリット・デメリットを理解してから、計画的に組むことが大切です。
まずは主となる3つに住宅ローンの特徴を見ていきましょう。
民間住宅ローンを利用してマイホームを購入する

主に銀行が提供している住宅ローンです。
利用者が多いこともあり、競争するかのように低金利のものが誕生しています。
審査は緩やかで、比較的通りやすいです。
多くの民間住宅ローンは、半年ごとに金利の見直しが行われる変動金利型を採用しています。
公的ローンを利用してマイホームを購入する
現在ある公的ローンは財形住宅融資だけです。
参考資料:財形住宅融資 住宅金融支援機構
利用条件は1年以上財形貯蓄を行っており、50万円以上の残高がある人。
5年ごとに見直しが行われる固定金利で、借入額の上限は4,000万円以内と低いです。
準公的ローンを利用してマイホームを購入する
フラット35などの全期間固定金利型住宅ローンのことです。

参考資料:フラット35
金利は銀行によって異なりますが、どれも期間中の金利は変わりません。
そのため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。
住宅ローン選びのポイントですが、やはり商品比較をしてみるのが一番です。
金融機関によって得意な金利タイプは異なります。
例えば、金利だけならネットバンクのほうが低いですが、手数料が高いうえに担当者との相談・打ち合わせができないという弱みがあるのです。
金利ばかりに目が行きますが、重要なのは保証料なども加えた総支払額。

総支払額が少しでも低いのを選ぶのが得策です。
マイホーム購入時の住宅ローンの組み方と流れ
事前申し込み
▼
事前審査
▼
正式申し込み
▼
本審査
▼
住宅ローン契約
▼
融資スタート
融資の実行日は、物件の引き渡し日となります。

そのため、申込時と物件引き渡し日では、金利が変わる可能性があるので要注意。
基本的には、住宅引き渡しの1か月前までにはローン契約を終えておきましょう。
マイホーム購入から引き渡しまでの期間と流れ

ここでは、マイホーム引き渡しまでの主な流れを紹介します。
期間は物件タイプや住宅メーカーにもよりますが、平均すると6か月ほどです。
ただし、早い建築メーカーや中古・マンション購入だと3か月以内で引き渡されます。
土地探しと購入
▼
建築会社の決定
▼
設計や工事の契約を結ぶ
▼
数回の打ち合わせを重ねプランが決定
▼
建築確認や長期優良住宅の申請
▼
住宅ローンの申請
▼
工事開始
▼
マイホームの完成と表示登記
▼
完了検査
▼
引き渡し
引き渡しが終われば、あとは引っ越しをして新生活のスタートです。
工事開始から引き渡しまでにかかる期間は3か月から半年。
ただし、工事開始前の打ち合わせや建築会社選びなどに時間がかかるかもしれません。
マイホームに入居するまでに必要な手続きや書類と流れ
 マイホームが完成して一息つきたいところですが、入居するまでに数多くの手続きを行わなければいけません。
マイホームが完成して一息つきたいところですが、入居するまでに数多くの手続きを行わなければいけません。
まず行うべきことが引っ越しですね。
引っ越しは3月中旬から4月上旬にかけてピークとなり、料金も割高になります。

予算をできるだけ抑えたいという方は、ピーク時の引っ越しを避ける、もしくは平日に引っ越しを行うといいでしょう。
そして引っ越しの際には、電気・水道・ガスの手続き、ネット回線変更手続き、住所変更手続きなどをしなければいけません。
特に重要なのが、役所で行う転出届と転入届の提出。

事前に必要な項目はリストにして、早め早めに取り掛かるといいですね。
以下が入居までの流れです。
念願のマイホームへの引っ越し前の手続き
引っ越し業者決め
現在住んでいる住宅の契約解除
▼
電気やガスなどの住所変更届の提出
持ち物整理と使わないものの梱包
▼引っ越し1週間前
転出届の提出
転居届の提出(郵便局)
国民年金の住所変更届提出
▼
引っ越し
マイホームに引っ越しをした後に必要な手続き
- 転入届と印鑑登録
- 引っ越し後から2週間以内に国民健康保険の再加入
- 国民年金手続き
- 銀行で住所変更
- 自動車ナンバー変更(他県へ引っ越す場合)
- 運転免許証の住所変更
マイホームを買った後は確定申告を忘れずに!

住宅を購入したあとは、確定申告をして払いすぎた税金を返してもらう必要があります。
確定申告時期は、入居した翌年の1月から3月15日までで、最寄りの税務署で申請しましょう。
サラリーマンなら、初年度のみ確定申告が必要です。
マイホームを購入した後に必要なお金

マイホームを買った後にも、様々な費用が出ていきます。
例えば、引っ越し代が代表的ですよね。
しかし、ここではマイホームにかかる税金について見ていきましょう。
購入するときには莫大な消費税がかかりますが、購入後にも固定資産税、場合によっては都市計画税がかかります。
マイホームには固定資産税がかかる
土地や建物所有者に対して、毎年かかる税金です。
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×標準税率1.4%。
重要となるのが固定資産税評価額です。

固定資産税評価額は、土地と家屋2つの要素で決定されます。
また、地方自治体によって標準税率が1.4%を上回る場合があります。
固定資産税の基準は各自治体によって異なりますが、基本的には長期優良住宅に対する減税措置が用意されています。
さらに、条件さえ満たせば土地に関する減税もあるのです。
マイホームを購入すると都市計画税が必要になるケースも
住宅を建てた場所によっては、都市計画税がかかるかもしれません。
都市計画税とは、都市計画区域内にある住宅に対して毎年1回課され、税率は最大で0.3%です。
都市計画税の対象となる地域は、主に以下の3つです。
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
マイホーム購入ブログ3選

マイホームを買った人の中には、その記録をブログとして公開している人々がいます。
ここからは、マイホーム購入者のおすすめブログを紹介します。
1.年収400万の新築マイホームブログ
世帯年収400万円で、お子様もいる方がマイホームを建てるまでの記録です。
このブログはコストを抑えたい方はもちろん、そうじゃない方もチェックしてください。
概算見積もりや値引きの内容、便利な間取り図などリアルすぎる有益な情報が満載です。
特にコストの抑え方や値引き術は必見!
2.家と家族と私
ミサワホームで自由設計住宅を建てられた方のブログです。
全てにおいて非常に細かく記録されているのがおすすめポイント。
ハウスメーカー選びから打ち合わせ、地盤についてなどなど参考になる記事が盛りだくさん。
初めから最新記事まで読みたくなるブログです。
3.ししまるさんの夢のおうちづくりdiary
理想のマイホーム作りから、完成後の日々までつづられているブログです。
真似したくなるアイデア満載のブログなので、理想のマイホーム像作りに参考になること間違いなし!
いい部分だけではなく、後悔している部分も紹介されているのは好感度持てますよね。
「どんなマイホームにしようかな?」と悩んでいる方は、きっと参考になるブログですよ。
マイホームを買うのに参考になる本や雑誌

マイホームに関する本や雑誌は数多くありすぎます。
どれを選ぼうかと迷われると思うので、ここからは私が実際に読んでおすすめできるものを厳選して紹介します。
1.マイホーム 理想を実現する購入ガイド
マイホームを購入したいと考えたら、まずは読んでおきたい1冊です。
マイホームの作り方から信頼できる会社の選び方、お金に関して、住宅ローン、そして入居後のことまで詳しく解説されています。
この雑誌を読んでおけば、とりあえずマイホーム作りで迷うことはありません。
易しい文体で書かれているので、初心者の方も楽に読み進めることができますよ。
2.マイホームはこうして選びなさい
戸建てやマンション、リフォームなどについて抑えておくべきポイントが詳しく書かれています。
少し専門用語が並びますが、情報の有益性は非常に高いです。
特に、大震災後は住宅選びの基準が変化しました。
家と人を守るマイホームを作りたい方は、読んでおいて損はない一冊です。
3.買ってはいけない家と土地
マンションにしようか、一戸建てにしようかと迷っている方におすすめの一冊。
この本の特徴は、とにかく幅広く物件種類について解説されていること。
住宅タイプや新築・中古で迷っている方の手引書となるはずです。
幅広い視点を持てるので、冷静に物件タイプを選べるようになりますよ。
一戸建てと決めていたのに、マンションのほうが向いていると思えるかもしれません。
4.最新版住宅ローン借り方・返し方 得なのはどっち?
住宅ローンは選び方次第で、数百万円得することもあれば損することもあります。
住宅ローンを考えている方は、一度真剣に勉強するのがおすすめです。
この本は住宅ローン入門書として最適な一冊。
住宅ローン選びで迷っている方は、ぜひ手に取ってみてください。
マイホームの失敗事例~後悔しない為に知っておきたい3つのこと
 夢のマイホームを建てたはいいものの、少しばかり後悔している人は一定数います。
夢のマイホームを建てたはいいものの、少しばかり後悔している人は一定数います。
失敗から学べることは多々あります。
そこで最後にマイホームの失敗例を見て、同じ轍は踏まないようにしましょう。
ケース1:マイホームにこだわりを持ちすぎたのはいいけど
よくある失敗事例が、こだわりを持ちすぎてマイホームを作ったものの、あまり必要性を感じていないというもの。

収納スペースをたくさん作る、設備は最新のもので揃えるなど、人によってこだわりは違います。
でも、せっかくのこだわりも使用しなければ意味ないどころか、費用の無駄になってしまうのです。
理想像を作る段階で、本当にそのこだわりが必要かどうか見極めるようにしましょう。
ケース2:マイホームを購入したけど、住宅ローンの支払いが大きな負担
年収や予算に見合っていない額を借りてしまったため、ローン返済が大きな負担になるのもよくある失敗事例。

やはり大事なのは、ある程度の頭金を準備しておくこと。
親から贈与を得られないようならば、親から借金をするのも手です。
今は順調でも将来的に年収が減る可能性があれば、生活費が増える可能性もあります。
そんな時に住宅ローンの返済でいっぱいいっぱいにならないよう、余裕のある額を借り入れるようにしましょう。
ケース3:マイホームを購入したけど、立地が合っていなかった
都心部から離れた場所にマイホームを建てる方は多いです。
しかし、毎日の電車通勤/通学が苦しくなったり、周りに何もなくて不便を感じたりするのはよくあること。

そう思っても、一度マイホームを建てた場所からは簡単に引っ越せません。
この失敗を防ぐためにも、土地購入前には周辺リサーチを徹底的に行いましょう。
すでにそこに住んでいるつもりで、一日を過ごしてみるのもいいですね。
まとめ
最後まで読んでくださり、ありがとうございます!
マイホームを建てるためには、何千万円という莫大なお金が必要ですが、守りたいことは以下の2つ。
- 住宅ローン選びは慎重に行う
- 最低でも全体の20%の頭金は用意する
まずは予算を考えずに、マイホームに求めるものをリストアップして、優先順位をつけましょう。
そして、予算内に収まるように理想のマイホーム作りをしていくだけです。
たくさん悩むかと思いますが、あなたが満足するマイホームを作れることを願っています!

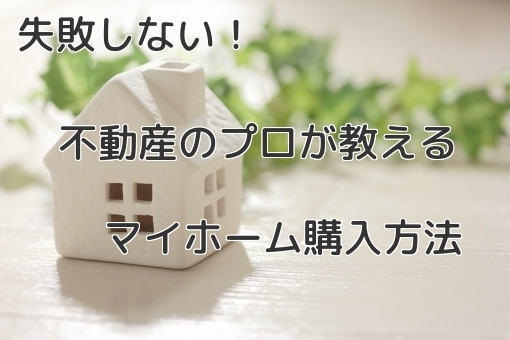









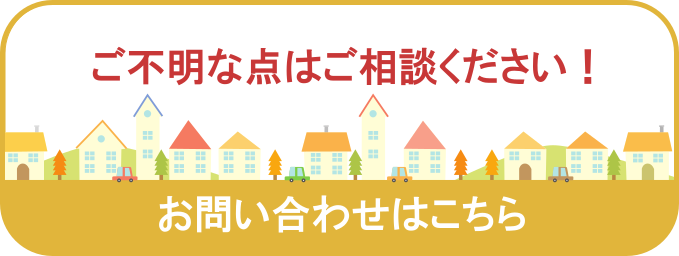





コメントを残す